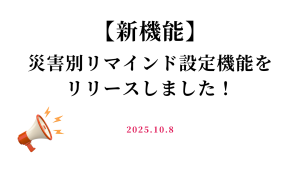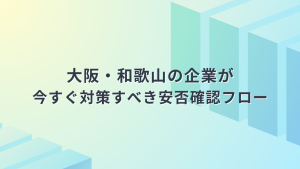南海トラフ地震に備える安否確認の重要性(静岡・愛知・三重編)
南海トラフ地震は、静岡県から宮崎県の太平洋沿岸にかけてのプレート境界を震源域とし、過去100〜150年の周期で繰り返し発生してきた巨大地震です。
2024年8月8日には宮崎県沖の日向灘でM7.1の地震が発生し、気象庁が初めて「南海トラフ地震臨時情報」を発表しました。
今後また臨時情報が発表されたときに焦らずに行動できるよう、「自分と大切な人を守るために、どんな準備をしておくべきか」
そして「情報が途絶えた中でどう安否を確認するか」も含めて解説します。
南海トラフ地震とは?
南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘にかけての「南海トラフ」沿いで発生するプレート境界型地震です。
過去には、昭和東南海地震(1944)と昭和南海地震(1946)がわずか2年の間隔で発生。
現在は発生から約80年が経過しており、地震調査研究推進本部によると、今後30年以内にM8〜9クラスが発生する確率は約80%とされています。
「南海トラフ地震臨時情報」とは?
気象庁が、南海トラフ沿いで異常な地殻変動や大地震を検知した場合に発表するのが「南海トラフ地震臨時情報」です。
発表段階は次の4種類
➀調査中:異常を確認し、関連性を調査中
②巨大地震注意:地震の発生可能性が一時的に高まった状態
③巨大地震警戒:さらに大規模な地震の発生が切迫している状態
④調査終了:特段の関連がないと判断された状態
「巨大地震警戒」が発表されると、自治体から「事前避難」が呼びかけられることもあります。
このとき慌てず行動するためにも、平時からの備えと情報共有のルール作りが欠かせません。
南海トラフ地震臨時情報が発表されたら?
「調査中」が発表された段階では、まだ避難行動を取る段階ではありませんが、
このタイミングから最新情報を確認し、避難準備・安否確認手段を整えることが重要です。
「巨大地震警戒」が出た場合、沿岸部の「事前避難対象地域」では、自治体が避難を呼びかけます。
企業も業務継続より命を優先し、従業員や利用者の避難を最優先に判断する必要があります。
● ここで大切なのが「安否確認の仕組み」
災害直後は電話やメールがつながりにくく、誰が安全か・どこにいるかが分からなくなるケースが多発します。
そのため、SlackやTeamsなど、日常的に使っているコミュニケーション基盤を活用した安否確認が有効です。
日頃からの備えと「安否確認のルール化」
【家庭・個人でできる備え】
・家族で避難場所・集合場所・連絡手段を決めておく
・ハザードマップで浸水想定区域を確認
・非常持ち出し品や懐中電灯、ヘルメットなどを枕元に常備
・デマ情報に惑わされないよう、気象庁・自治体・政府広報など公的情報源を確認
【企業・自治体でできる備え】
・防災マニュアルや安否確認フローを整備
・Slack・Teamsなどを活用した安否確認サービスの導入
・定期的な防災訓練や情報伝達テストを実施
・一部従業員が出社できない前提で事業継続計画(BCP)を策定
静岡・愛知・三重編:安否確認が命をつなぐ
南海トラフ地震の被害想定地域の中でも、静岡・愛知・三重の3県は、震源域に隣接し、最も早く大きな被害を受ける可能性が高いエリアです。
この3県では、揺れ・津波・ライフライン断絶・通信障害が同時多発的に発生すると想定されています。
そんな状況下で「社員の安否」「家族の安否」「住民の安否」をどう確認するかが、命を左右します。
■ 静岡県
静岡県は、古くから「東海地震の震源域」として警戒が続けられてきました。
駿河湾沿岸では最大クラスの津波被害、内陸の山間部では土砂崩れや孤立集落の発生が懸念されます。
また、首都圏と中京圏を結ぶ交通の要衝であるため、被災後は物流の分断・孤立化が発生しやすい地域でもあります。
【課題】
・停電・通信断の中での社員や住民の安否確認
・帰宅困難者・通勤途中の従業員対応
・行政・企業間の情報共有の遅れ
■愛知県
愛知県は、自動車・製造・物流の中核を担う日本屈指の産業集積地です。
しかしその強みゆえに、一社・一拠点の被災が他社や全国供給網に波及するリスクがあります。
また、沿岸部(名古屋港・知多半島)では津波被害、内陸部でも長周期地震動による高層ビルの揺れが懸念されています。
【課題】
・工場・本社・在宅勤務者をまたぐ即時安否確認
・従業員数が多く連絡手段が錯綜しやすい
・災害時の拠点間連携・BCP発動の遅延
■三重県
三重県南部(尾鷲・熊野・志摩など)は、津波到達が非常に早い地域として知られています。
揺れを感じてから津波が来るまで、わずか数分というケースもあり、
「揺れたら逃げる」「逃げながら伝える」という意識づけが生死を分けます。
【課題】
・津波発生時、現場が混乱し安否把握が遅れる
・広域避難による従業員・住民の所在不明
・山間部では孤立集落化し、救助要請が届かない
アンピーで広がる“つながる防災”
アンピーは、Slack(最近Teams版もリリースしました!)と連携して使える安否確認サービスです。
災害情報を自動で通知し、メンバーの安否をワンクリックで報告・確認できます。
ネットワークが不安定な状況でも、普段使っているチャット環境内で完結するため、
緊急時でも「伝わらない」「確認できない」を防ぎます。
“備え”とは、システムを導入することではなく、「いざという時に確実に人の無事を確認できる体制を作ること」。
アンピーは、その第一歩をサポートします。
まとめ
南海トラフ地震は「いつか必ず来る」と言われています。
その“いつか”に備えるために大切なのは、正しい知識・確実な連絡・日常の意識づけです。
防災バッグの準備や避難経路の確認とあわせて、大切な人のために「安否確認体制」も整えておきましょう。
アンピーは、災害時に誰もが安心できる環境を届けることを目指しています。
普段お使いのSlackやTeamsをそのまま活かしながら、
「守れる組織づくり」を一緒に進めていきましょう。
ただいま1ヶ月間の無料お試しをご利用いただけます。
リスクなく導入でき、お申し込み後すぐにご利用を開始可能です。
まずは、アンピーの「使いやすさ」と「安心感」を体験してみてください。
▼ アンピーについてはこちら
▼ 資料請求はこちら