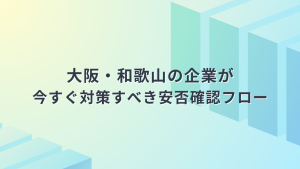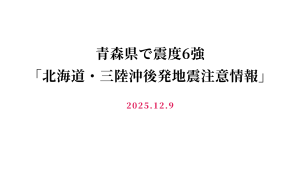東海・関西企業が今こそ備えるべき「安否確認体制」
南海トラフ地震は、政府の想定でも30年以内の発生確率70〜80%とされています。
静岡・愛知・三重・大阪・和歌山・兵庫といった広範囲が震源域・津波被害想定地域に含まれます。
地震が発生すれば、通信インフラや交通機関はまひし、初動1〜2時間での情報共有が生死を分けると言われています。
企業が直面する課題:「社員の安否がわからない」
過去の地震では、「誰が無事で、どこにいるのか」が把握できず、初動対応が遅れた企業が少なくありません。
災害時は電話が一斉に使われて回線が混み合ったり、メールの送受信が遅れたりして、連絡が取れないケースが多発します。
その結果、安否確認に数時間〜半日を要し、「誰が無事か」「どの拠点が動けるか」が見えないまま救助や業務再開の判断が遅れ、それが二次被害や混乱を招く最大の要因となりました。
“情報が届かない”ことこそが被害拡大を生む。
だからこそ、安否確認体制の見直しが今、求められています。
東海・関西企業が特に備えるべき理由
● 東海エリア(静岡・愛知・三重)
津波到達が早く、沿岸部の工場・拠点リスクが高い。
製造業では稼働再開判断が経営を左右します。
● 関西エリア(大阪・和歌山・兵庫)
交通網の寸断・帰宅困難者対策が大きな課題。
都市部の情報共有スピードが復旧の鍵になります。
「初動1時間」を守れる企業に
BCPは計画書ではなく、「動ける仕組み」でこそ意味があります。
アンピーのようなツールを導入すれば、訓練〜実際の災害時まで、同じ操作で安否確認が完結します。
「今」できる備えで、「その時」に迷わない組織をつくりましょう。
Slackで「動く」安否確認へ
今、注目されているのがSlackやTeamsなど、企業が日常的に使っているチャット上で動く安否確認です。
普段のコミュニケーションツールを使うメリット
・通信が比較的安定している
・即時通知・自動集計が可能
・管理者がリアルタイムで全体を把握できる
たとえばアンピーでは、
● 災害発生をSlackチャンネルにリアルタイム通知。
● 社員はボタン1つで安否を報告でき、結果がリアルタイム反映。
災害時の“情報断絶”を防ぎ、混乱の中でも確実に動ける仕組みです。
BCPの第一歩は「人を守る仕組み」から
東海・関西エリアの企業にとって、今、必要なのは「実際に動く安否確認体制」を整えることです。
「いざというとき」に動ける会社と動けない会社、その差を分けるのは日ごろの準備に他なりません。
普段の業務フローの延長で使えるアンピーなら、社員の安全を守りながら、事業継続に向けた一歩をスムーズに踏み出せます。
今こそ、人と事業の両方を守る仕組みを整えましょう!
▼ アンピーについてはこちら
▼ 資料請求はこちら